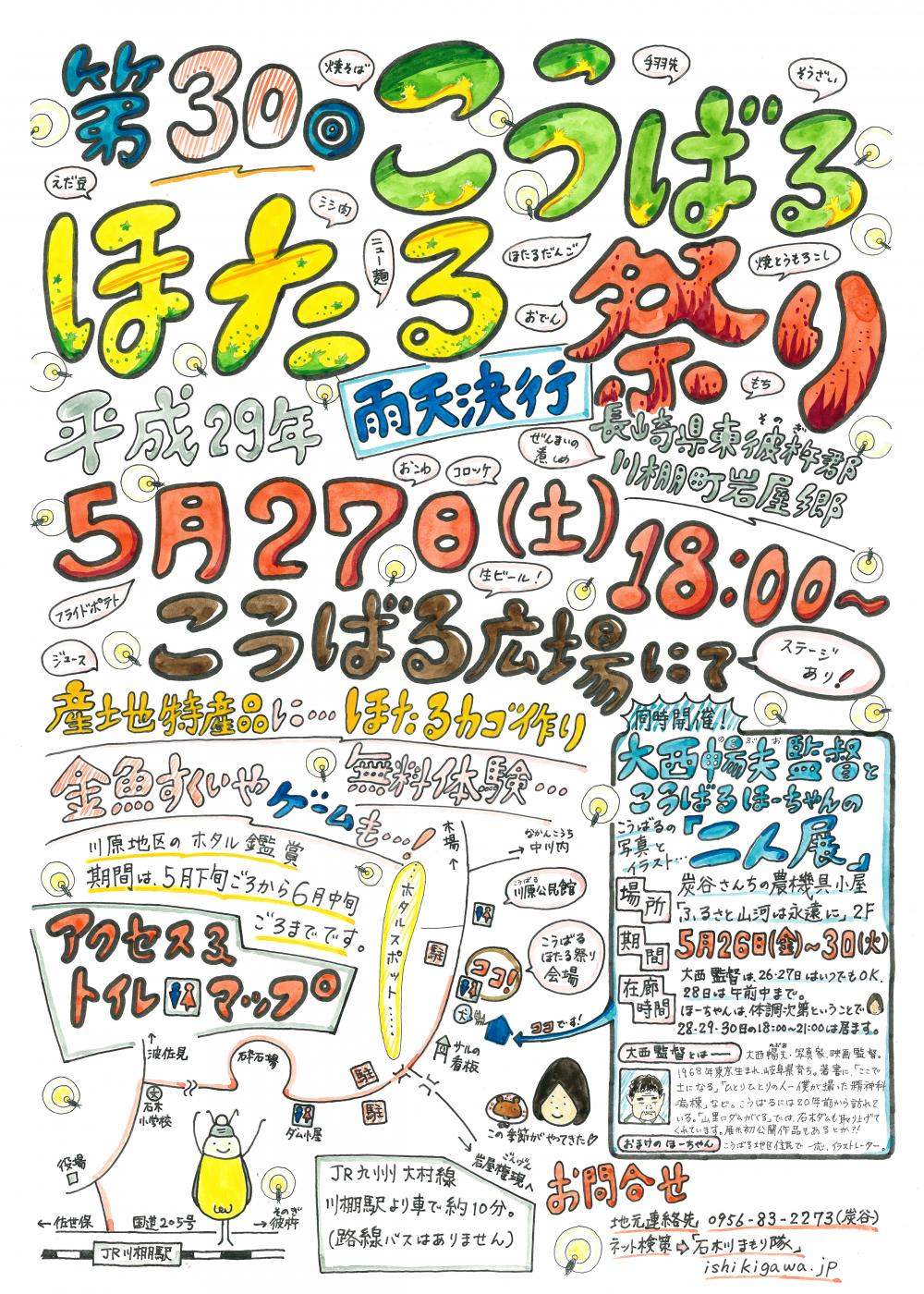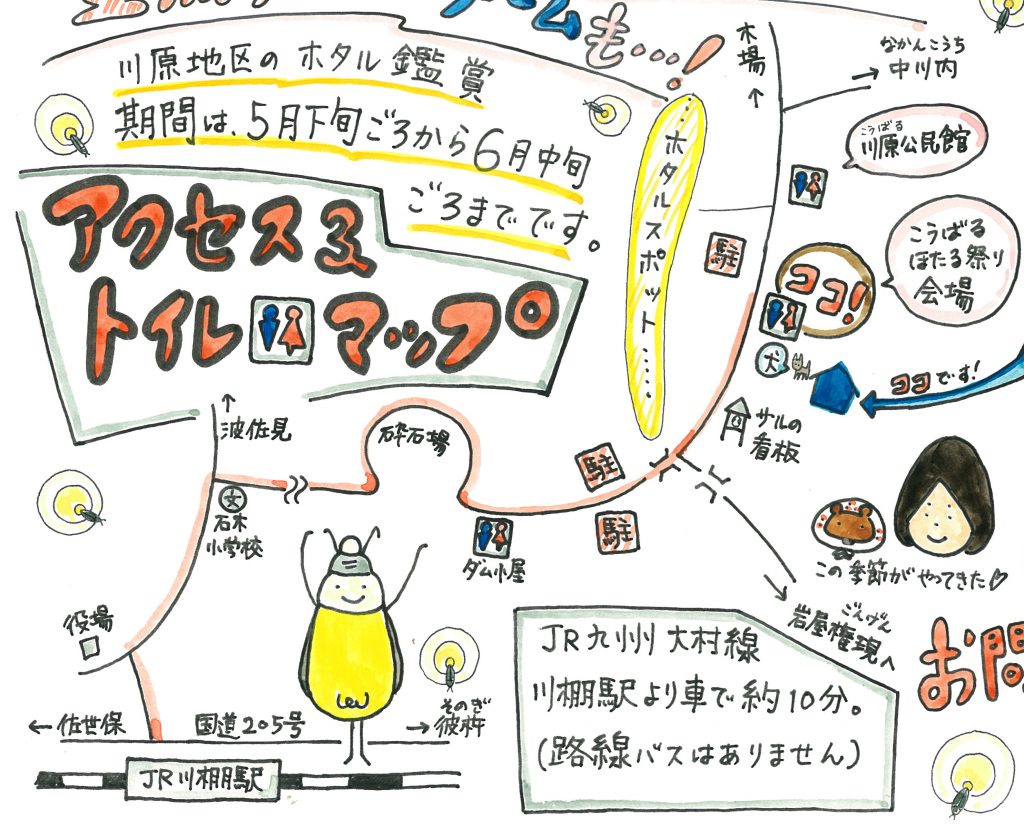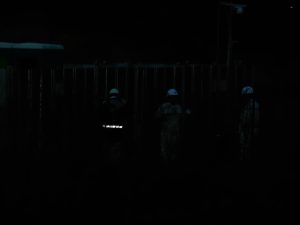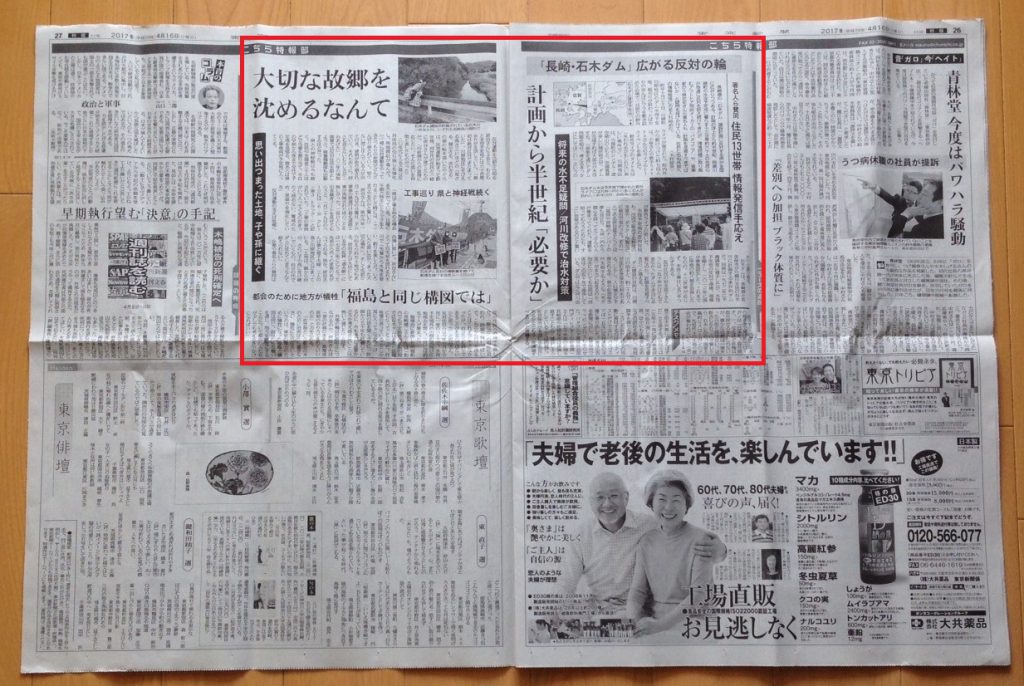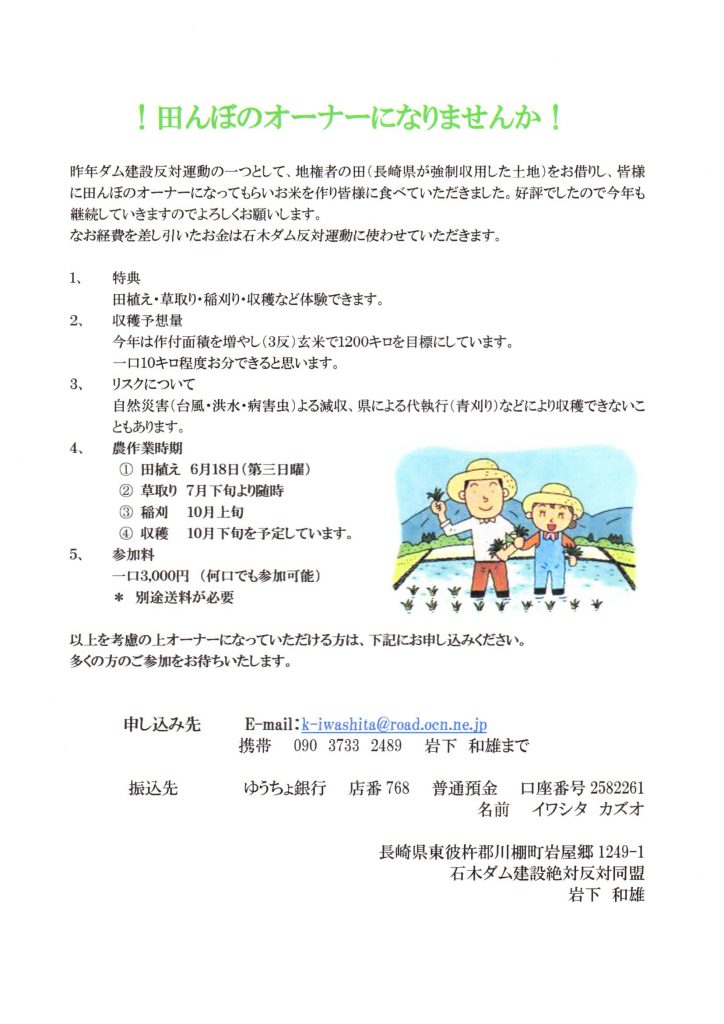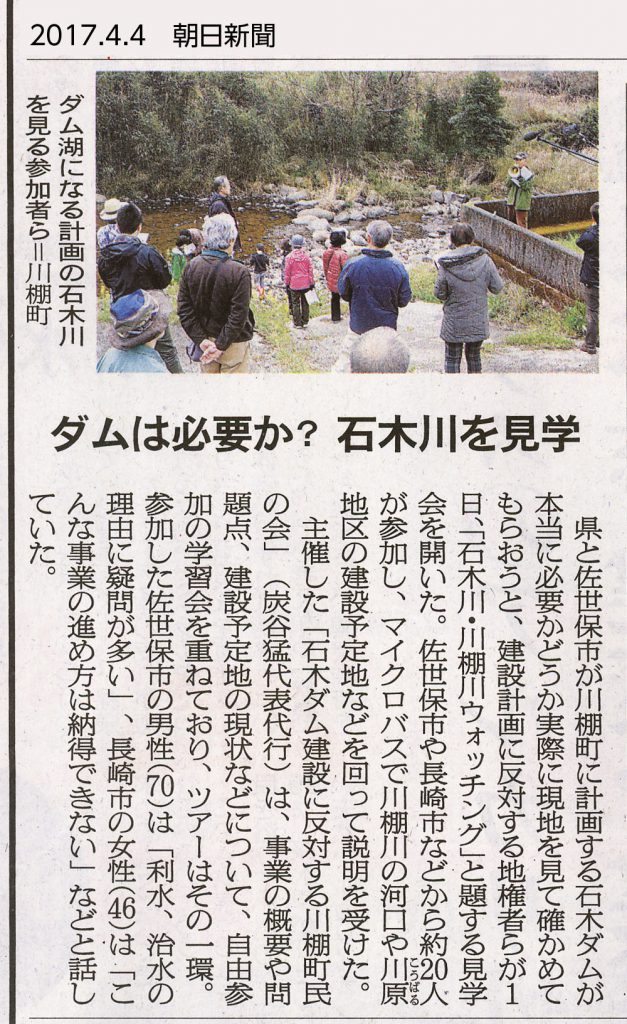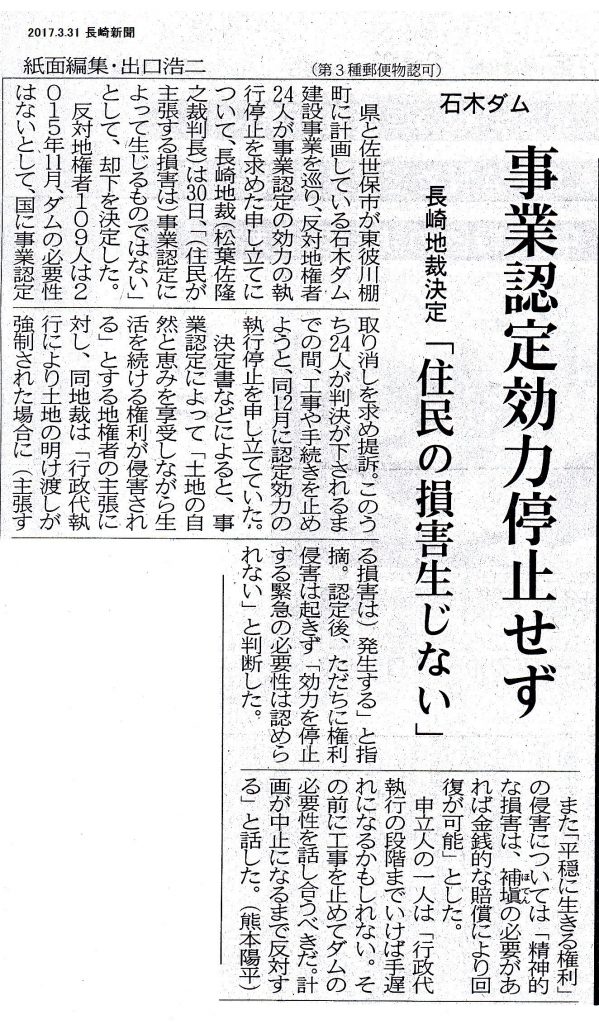つい先日、こうばる住民のお一人から届いたメールを紹介します。
ある婦人がこう言った。「主人が生きている間に石木ダムが出来なかったら…死ぬにも死にきれない」
私がダム水没予定地の住人だと知りながら。
すでに4家の土地(田畑)が強制収用されようとしていることもニュースでやり始めた頃の話だ。
婦人によるとご主人は、当時役場の建設課のお偉いさんだったようで、町長さんにいろいろ言われながら過ごした。それも数年間も。
だから、ダムを造って欲しいのだそうだ。
涙まで流してみせた。それで…?
私は呆気に取られた。
元役場職員ならば、町民にとって何が大事なのか考えること。
今は役職考えずに正しいと思うことが言えるはず…。
それになんで婦人にお願いされなければならないのか?
私はきっぱり「それは残念ですね〜。私たちはずっとこうばるに住み続けるので…。」それだけは伝え、その他のいろんな想いは飲み込んでおいた。
なんのためにダムを造りたいのか…。
呆れてしまった。この問題についてどこまで知っているのか?(内容はさっぱり知らない様子だった)
こうばる住民は50年もの間ずっと付きまとうこの問題に悩まされているのに、たった数年辛かっただけで何を言っているのか?
私たちはいつまで続くかわからない闘いを続けているのに…。
こんな町民がまだまだいるのかと思うと、とても寂しい気持ちがした。
ずっと前に書き留めておいていたものです。
誰かに伝えたかったので…。
送ります。
このメールをくださったこうばる住民のXさんの心には、今も婦人の言葉がトゲのように刺さったままです。でも、婦人はそれを知らない。婦人に悪意はなかったので、きっと忘れていることでしょう。
こういうのを「悪意なきイジメ」というのでしょう。
悪意はないけれど、自分の視点のみで物事を考え、その考えを無邪気に口にする。相手の心情など想像することもなく。
今そんな人が増えているような気がします。
これだけ情報が溢れ、容易に入手できるにもかかわらず、客観的な情報など知ろうともせず、不利益を被る人の想いなど「忖度」しようともせず、自分たちにとって有益ならそれでいいと。
そして、悪意なきイジメが増えていくのを、悪意ある人々は利用します。
それを防ぐために、私たちにできることは何でしょう。
やはり事実を真実を、一人でも多くの人に伝えていくしかないのでしょう。
石木ダムが佐世保市民や川棚町民にとって、どれほど大きな不利益をもたらすかということを。